こんにちは、Tina Blogへようこそ。
今日は「猫の膀胱炎」に役立つ療法食(フード)について、
獣医の視点からやさしくお伝えしていきます。
「最近トイレに何度も行ってる…」
「おしっこが少ない気がする…」
そんな小さな変化から始まる猫の膀胱炎。
実は、毎日の“ごはん”が予防や再発防止のサポートになることをご存じですか?
猫の膀胱炎とフードの関係
猫の膀胱炎には、いくつかのタイプがありますが、
特に多いのが「特発性膀胱炎」と「尿石症(ストルバイト・シュウ酸カルシウム)」。
膀胱や尿道に炎症を起こしたり、結晶や結石ができると、
排尿時の痛みや血尿、頻尿、尿閉などの症状が現れることがあります。
ここで大切なのが、「水分」と「尿の成分バランス」。
食事によってこれらをコントロールしやすくするのが療法食の役割です。
療法食の役割とは?
療法食は、特定の病気や体調に配慮して栄養設計されたフードです。
膀胱炎対策用のフードには以下のような特徴があります。
- 尿を適度に酸性に保つ(特にストルバイト対策)
- 尿中のミネラルバランスを調整(カルシウム・マグネシウムなど)
- 水分を摂りやすくするウェットタイプや高含水フード
- 特発性膀胱炎に配慮したストレス軽減成分(加水分解ミルクプロテインなど)配合のものも
📚 参考:WSAVA(世界小動物獣医師会)の栄養ガイドライン、ロイヤルカナン公式資料、Hill’s資料 など
よく使われている療法食(日本でも入手可)
① ロイヤルカナン「ユリナリーS/O」シリーズ
- ストルバイトとシュウ酸カルシウム結石の管理
- ドライ&ウェットあり
- pHバランスと尿量のコントロールに配慮
② Hill’s(ヒルズ)「c/dマルチケア」
- 尿路疾患に配慮した設計
- ストレス軽減成分入り(c/dコンフォートの場合)
- ヒルズ独自の栄養バランス設計
③ ピュリナ「UR(ユリナリー)」
- 味のバリエーションが豊富(高いけど嗜好性◎)
- 結石の再発防止に配慮されたpH管理
- ウェットもあり、食欲の落ちた子にも対応
💡 ティナはまだ療法食は使っていませんが、
「将来必要になった時の選択肢」として、普段から調べておくようにしましょう。
注意点:療法食は「必ず獣医師の指導のもとで」
療法食は薬に近いフードと考えてください。
状態に合わないものを与えると、逆に悪化することもあるため、
- 尿検査の結果に応じて
- 結石の種類によって(酸性 or アルカリ性尿の調整が異なる)
- 体調や持病を加味して
獣医師の診断と指導のもとで始めることが大切です。
おうちでできるプラスαのケア
ごはんとあわせてできるサポートもいくつかご紹介します。
- お水を飲む工夫(自動給水器やスープタイプのおやつ)
- トイレ環境の見直し(猫の数+1個、静かな場所に設置)
- ストレスを減らす(急な模様替えや来客に配慮)
- 毎日の観察(おしっこの回数、色、量)
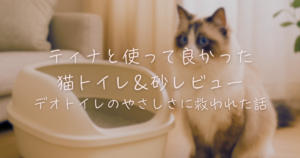
まとめ|毎日のごはんが、猫の健康を支える
膀胱炎は繰り返しやすい病気ですが、
「ごはん」という身近な方法でケアができるのは、飼い主にとって心強いですよね。
- 適切な療法食を選ぶこと
- 水分とトイレ環境に配慮すること
- そして、何より猫ちゃんの“いつもと違う”を見逃さないこと
この記事が、猫ちゃんの健康管理に悩む飼い主さんのヒントになればうれしいです🐾
※本記事は情報提供を目的としたものであり、治療や診断を代替するものではありません。療法食の使用については、必ず獣医師の指導を受けてください。

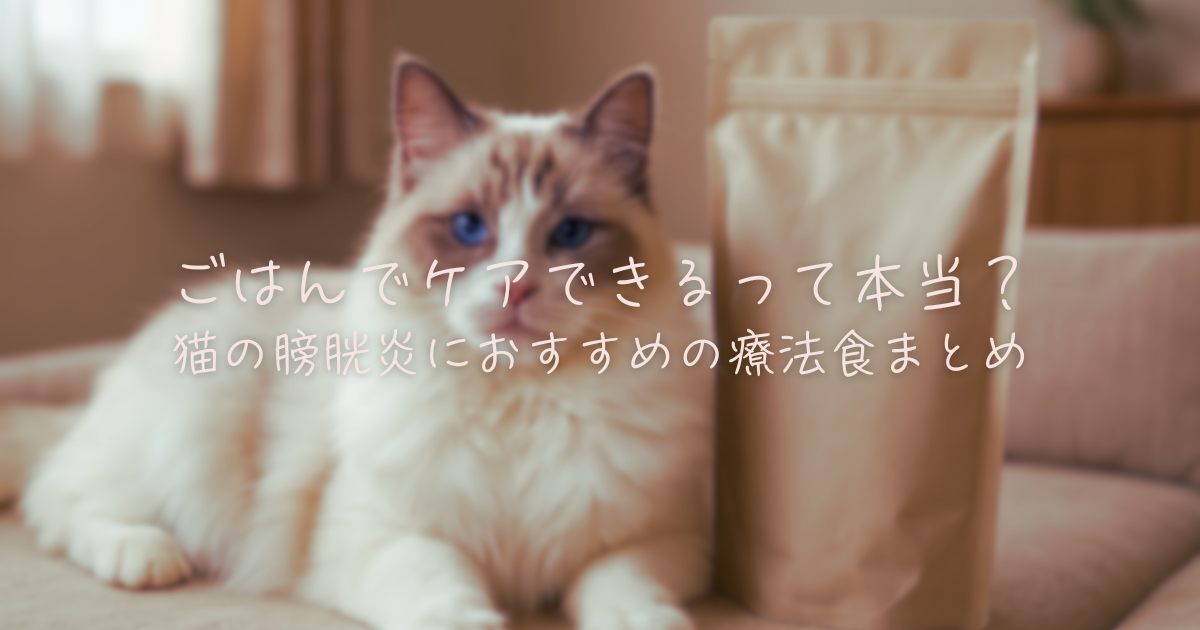
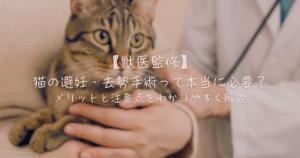
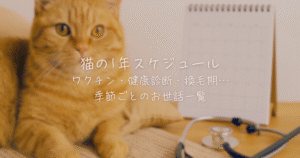
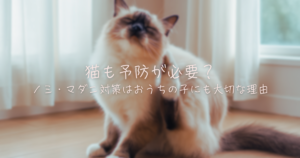
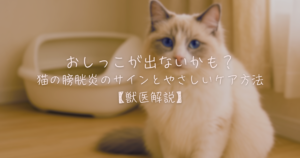
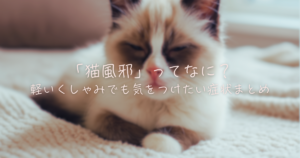
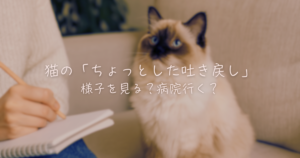
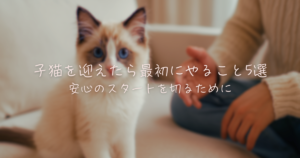
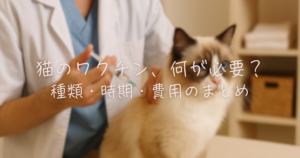
コメント