こんにちは、Tina Blogへようこそ。
今回は「猫の避妊・去勢手術ってやっぱりやった方がいいのかな?」と悩んでいる方に向けて、
その目的やメリット、注意点についてやさしく解説していきます。
私自身もティナを迎えたときに、どのタイミングで手術を受けさせるべきか悩みました。
でも、正しい情報を知ることで、納得して決断することができました◎
避妊・去勢ってどういうこと?
避妊・去勢手術とは、それぞれ以下のような手術です。
- 避妊手術(メス):卵巣や子宮を取り除く手術
- 去勢手術(オス):精巣を取り除く手術
いずれも繁殖能力をなくすための手術ですが、目的はそれだけではありません。
病気の予防や行動の安定にもつながるとても重要なケアなのです。
なぜ必要?避妊・去勢の主な目的
✅ 1. 望まない妊娠を防ぐ
猫は性成熟が早く、生後6〜8ヶ月ごろには妊娠が可能になります。
1回の出産で4〜6匹の子猫が生まれることもあり、無計画な繁殖は飼い主にも猫にも負担が大きくなります。
→【参考】日本小動物獣医師会「飼い主向けパンフレット」
✅ 2. 発情によるストレスを減らす
発情期になると、メス猫は大きな声で鳴いたり、落ち着かなくなったりします。
オス猫は発情中のメスのフェロモンに反応して、脱走・スプレー行動(マーキング)が増える傾向に。
これらの行動は猫にとってもストレスですし、飼い主にとっても生活の支障になりがちです。
→【参考】猫の行動学に関する文献:Crowell-Davis SL et al., J Feline Med Surg. 2004.
✅ 3. 病気の予防につながる
避妊・去勢によって、以下のような病気のリスクを減らすことができます。
メス猫の場合
- 子宮蓄膿症(命に関わる子宮の感染症)
- 乳腺腫瘍(早期の避妊で90%以上リスク減少)
オス猫の場合
- 精巣腫瘍
- 攻撃性・ストレスによる排尿トラブル
→【参考】AVMA(米国獣医師会)2021年発表資料
手術はいつ受ければいいの?
一般的には生後6ヶ月前後で手術を行うことが推奨されています。
近年では、より早期の「早期不妊手術(Early Spay/Neuter)」も安全に行われるケースが増えています。
ただし、成長のスピードや健康状態によっては時期を調整した方がよい場合もあるため、かかりつけの獣医師と相談しながら決めましょう。
→【参考】WSAVA Global Veterinary Guidelines, 2020.
避妊・去勢後の変化と注意点
✅ 穏やかになるけど「性格が変わる」は誤解も
発情に伴うイライラや攻撃性が軽減され、全体的に落ち着いた印象になることはあります。
でも、猫の本来の性格まで大きく変わるわけではないので安心してください。
✅ 太りやすくなる?
避妊・去勢後は基礎代謝が下がるため、食事量や運動量の管理が大切になります。
適切なフードに切り替える、遊びの時間をしっかり取るなどで十分に対処できます◎
手術に関する不安について
「全身麻酔が心配…」という声もよく聞かれます。
ですが、現在の動物医療では術前検査・麻酔管理・術後ケアの技術が進歩しており、安全性は非常に高くなっています。
不安な点は、遠慮せずに動物病院で相談してみましょう。
まとめ|避妊・去勢は“愛情”のかたちのひとつ
猫の避妊・去勢手術は、「ただ妊娠を防ぐための処置」ではありません。
猫が健やかに、ストレスなく暮らしていくための大切な選択肢です。
「本当に必要なの?」と迷っている方にこそ、
正しい情報をもとに納得して判断してもらえたらうれしいです◎
※本記事は一般的な情報に基づいて作成しています。個々の猫の健康状態によって最適な時期や方法は異なりますので、かかりつけの獣医師とご相談ください。

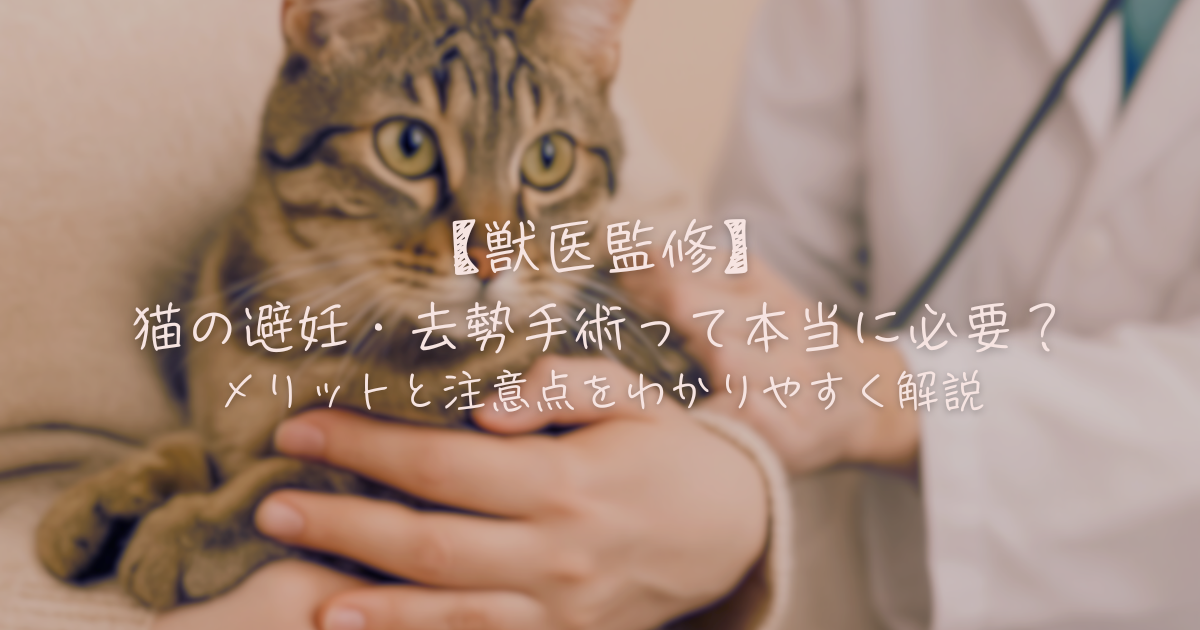
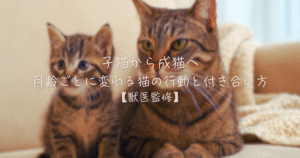
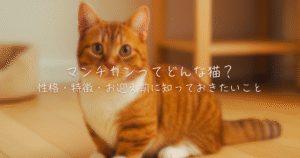
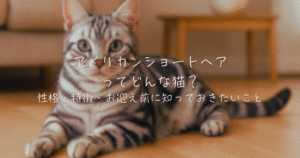
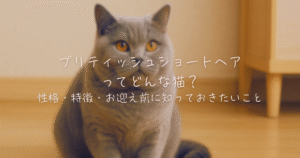
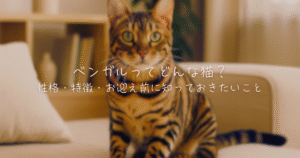

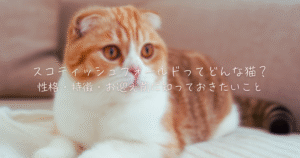
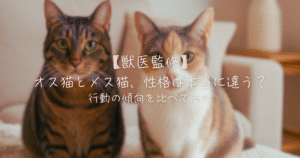
コメント